幼稚園で「話さなかった」私のこと
私は幼稚園の頃、今でいう「場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)」のような状態だったと思います。
家では普通にしゃべるのに、幼稚園ではほとんど話さない。出席の返事や劇のセリフなど、決まった場面では声が出せたのに、それ以外はなぜか話さない。今思えば不思議ですが、当時の私はそれが「普通」でした。
喋った最後の記憶
そんな私にも、幼稚園で話した記憶があります。
ある日、クラスの男の子の持ち物がなくなって大騒ぎに。誰かが冗談で「あなたが盗ったんじゃないの?」と茶化しました。私はとっさに「とってないよ!ほら!」と自分のかばんを開けました。すると、中には彼の持ち物が……。知らないうちに、自分のだと思ってしまい込んでいたんです。
私は慌ててそれを返しました。でもその後の記憶はあいまいです。はっきり覚えているのは、「ちゃんと説明できなかった」「わざとじゃないのに悪者にされた」そんな後味の悪い感覚だけ。
思い返すと、それが私が幼稚園で最後に話した記憶かもしれません。
話せなかったというより、「話さなかった」
「場面緘黙症」とは、話したいのに声が出ない――という状態だとされています。でも私の場合は、ちょっと違っていたかもしれません。
確かに話すのを避けていたけど、それは「自分の話をちゃんと聞いてもらえない」とどこかで感じていたから。傷つくくらいなら話さないほうがいい、そんな自己防衛だったのかもしれません。
幼稚園の思い出は、少し苦い
喋らなかったことで、他のクラスの女の子にいじめらたり、やりたくない体操教室に入れられたり、幼稚園の思い出はあまり良いものではありません。
でも、2年間で休んだのは体調不良の1日だけ。卒園式で表彰されました。どこかで「ちゃんと通わなきゃ」と思っていたのかもしれません。不思議な子どもだったなと、自分でも思います。
話せなかった私が、話せるようになった日
小学校に入ってから、私は自然と話せるようになりました。
その理由を今思い返すと、いくつかの「安心できる要素」が重なっていたのだと思います。
まず、幼稚園で一緒だったお友達が同じクラスにいてくれたこと。すでに知っている子がいるという安心感は、とても大きかった気がします。
それから、担任の先生がとてもおおらかな方でした。ベテランの女性の先生で、母が面談のときに相談したところ、「あの子はあの子なりにいろいろ考えているんだろうから、大丈夫よ」と笑っていたそうです。その寛容なまなざしが、私の「話してもいいんだ」という気持ちを育ててくれたのかもしれません。
また、勉強はわりと得意で、授業では自信を持てる場面も増えました。運動は苦手でしたが、スイミングスクールに通っていたので水泳だけは得意で、プールの時間にみんなに褒めてもらえたことも、自信になったと思います。
誰かに受け入れてもらえる、得意なことがある、自分なりのペースを尊重してくれる大人がそばにいる――そんな環境が、少しずつ私の「話せない心」をほぐしてくれたのだと思います。
この経験が私に与えたもの
あのときの体験が、今の自分にどう影響しているのか――正直、今でも時々考えます。
でも、大人になった私は、そこそこ幸せに暮らしています。自己肯定感もそれなりに高め。きっとその後の人生で、良い人たちに出会えてきたからだと思います。
もしお子さんが「話せない」なら
もしかすると、今これを読んでいるあなたのお子さんが、かつての私のように「話せない」状態かもしれません。
でも、それはその子の心が壊れているわけではなく、「安心して話せる場所や人」がまだ見つかっていないだけかもしれません。
子どもは思っている以上に、深く傷つきやすく、繊細です。そして、自分の気持ちをうまく言葉にできる力は、時間と共に少しずつ育っていくものです。
焦らず、責めず、その子の「話せない気持ち」に寄り添ってあげてください。きっと、必要なときに、自分の声で話し始められるようになりますから。
もしこの記事が誰かの心に届いてくれたら、とても嬉しいです。
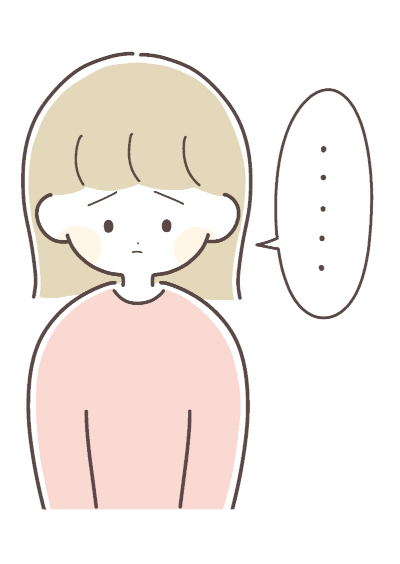


コメント